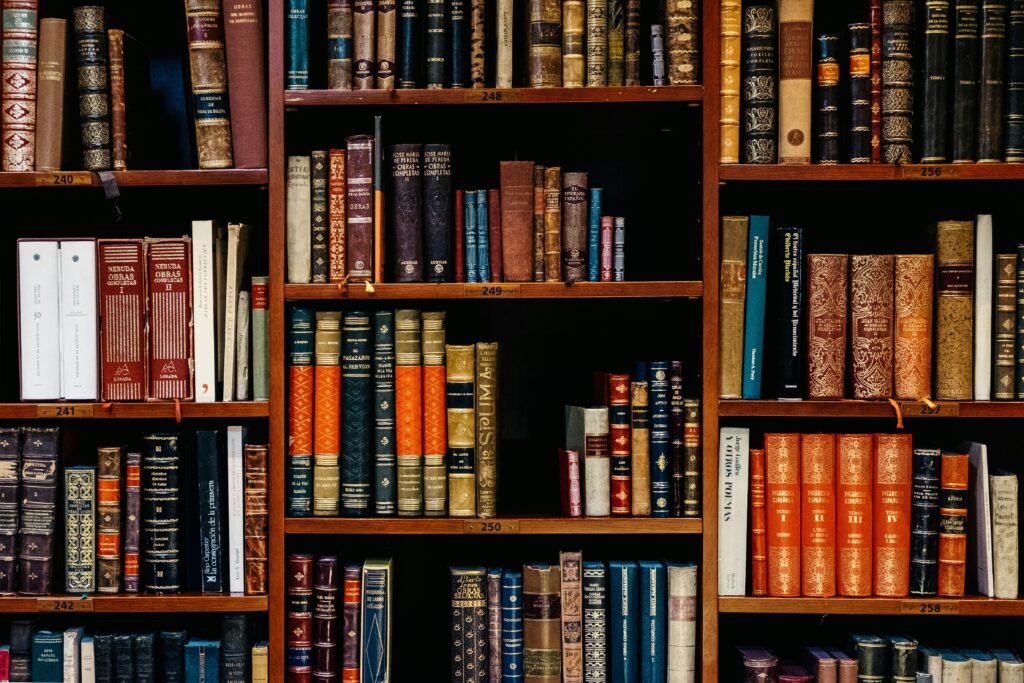
同人誌には、合同誌というものがある。合同誌とはアンソロジー本とも呼ばれ、複数の作者が集まって一冊の本となった作品集だ。今回はその魅力や制作プロセスについて解説しよう。
そもそも、合同誌(アンソロジー)って?
合同とは、複数の物がひとつに纏まること。アンソロジー(anthology)は、「選集」や「編集物」を意味する英単語であり、それらがそのまま同人用語としても使われるようになった。一般的には、複数の作者が一つのテーマやジャンルに基づいた作品を寄稿し、一冊にまとめたものを指す。アンソロジーはアンソロと略されることも。

合同誌にはさまざまな形態があり、大きく分けて2つ。
- テーマベース
- 特定のテーマに基づく。例えば前日譚・後日譚の想像、現代パロディ、イベント系に焦点を当てるなど。
- 作品ごとに様々な特色が出る。
- キャラベース
- 特定のキャラクターや集団、または特定のカップリングに焦点を当てている。例えば、A(キャラクター名)オンリー、○○オンリー(作品内の組織や括りなど)、A×Bオンリーなど。
- 縛りはキャラクターのみのため企画しやすく、作りやすい。
- 女性向け作品によく見られる。
合同誌の作り方

「この作品のこんな作品集が欲しい!」と思ったら、それは合同誌立ち上げの合図。同人誌は、何事も本人の欲望から始まる。
- テーマの決定
合同誌を作る際には、まずテーマを決めよう。テーマは版権元のガイドラインに違反しない限り、基本的に自由。ニッチな内容でも構わないが、募集をかけるのであれば、多くのメンバーが興味を持ち、かつ熱心に取り組めるテーマを選ぶことが重要。いいテーマであれば手に取ってくれる人も増えるだろう。 - メンバー集め
合同誌は一人では成り立たない。公募にするか、私募(自分でスカウト)にするか決めよう。
公募・・・主にTwitter(現・X)で発表し、ツイプラで参加表明を取ることが多い。
私募・・・主催者が自分で、描いてもらいたい人に声をかける。挨拶と理由をきちんと添えよう。 - 役割分担
基本的に主催の一人仕事。人数集めから入稿・頒布まで全て行う。参加者に原稿に集中してもらうためだ。参加者間で役割を分担する場合もある。 - 原稿の制作
版権元のガイドラインに則り、作成してもらおう。守ってほしいNG集を明記しておけば、参加者も問題なく執筆できるだろう。 - 編集と校正
各参加者から提出された原稿を確認し、配置するページを決定。もし不備があれば、修正を依頼する。 - 入稿
全ての原稿にもう一度目を通し、印刷会社に入稿。データ形式で頒布する場合は、公開するサイトを決定。 - 宣伝と配布
合同誌を広く知らせるために、頒布前に宣伝活動を行う。SNSを活用して、合同誌の存在を知ってもらおう。通販をする場合は、通販分の在庫を確保しておこう。
以上が一般的な合同誌の作成手順となる。
3の役割分担に関しては、必ずしも主催一人で行う必要はない。具体的な手法や流れは、合同誌の規模や参加メンバーに応じて変わる場合があるぞ。
合同誌の魅力

合同誌には、一個人で発行する同人誌とは一味違った魅力がある。特定のテーマに沿ったイラストや物語をそれぞれの作者が表現することで、新しい視点からの発見や考察を得ることができる。このように多様な作品が一冊の本に集約しているため面白く、飽きることなく何度も読み返したくなることだろう。もちろん参加者の質によるが。
まとめ
合同誌は、多様な参加者が集まる、テーマに則った魅力的な作品集だ。王道テーマからニッチなものまで、ジャンルによって様々なテーマがあるのが面白い。ぜひ一度、自分の興味あるジャンルの合同誌に触れてみてはいかがだろうか。自分の中で新しい世界が広がるかもしれない。